明けましておめでとうございます。武蔵野レコード石井です。
今日は5日で、明日から仕事始めなんですが、毎日10時間近い睡眠を貪っていたせいか仕事モードに全然なりません。リハビリがてら「2019年のベストレコード」を書こうと思います。
でも皆さん、何が2019年に買ったレコードかなんて覚えていますか?って言ったら、中川さんに「ちゃんとExcelで管理しなきゃダメなじゃないですか!」って怒られちゃいました。中川さんは、ムサレコでかけたレコードもExcelで管理しているようですよ、マメだなあ。
グダグダ言っていないで始めてみたいと思います。あ、ぼくは旧譜オンリーです。
TUFANO & GIMMARESE“THE OTHER SIDE” (1977)
これ、裏ジャケがまったく同じ写真でミュージシャン・クレジットがなかったのでジャケ買いです。こういう青春AORな香りのする裸の男子二人組ってそそりますよね?後で調べてみたらこの二人はキャノンボール・アダレーのヒット曲「Mercy, Mercy, Mercy」に歌詞をつけてヒットさせたザ・バッキンガムズのフロント二人でした。このアルバムの一曲を除く全曲が二人の作詞作曲です。
家に帰りインナースリーブのクレジットを見て小さくガッツポーズをしたのですが、ベースにはチャック・レイニー、ピアノはリチャード・ティー、ギターにはレイ・パーカーやジェイ・グレイドンなど鉄壁のミュージシャンたちがバックを固めています。これ、まさに狙い通りの青春AORの爽やかな名盤です。惜しむらくは二人とも名前が難しい!

これが問題の裏ジャケ。ちょっとナメてる。

THE KEANE BROTHERS“TALKING OFF” (1979)
この人たちもよくわからないんだけど、ドラムにジャームズ・ガドソン、ベースがスコット・エドワード、キーボードがデビッド・フォスターとデビッド・ペイチと、照れくさいジャケから青春AOR臭がプンプンとしてきたので即買いでした。TUFANO & GIMMARESEを青春硬派AORとするなら、こいつらは軟派AORですね。絶対にモテるために音楽やってるヤツらです。
パーティー感というか終始浮ついていて、音的にはディスコの夜明けを感じさせつつ、しっかりと地に足の着いたAORを奏でています。落とすときはマジみたいな。この辺が1979年の面白いところですよね。
青春AORの魅力は、長い人生の中の瞬間でしかない“儚さ”にあると思います。その儚さを日本人の英語のわからないリスナーが一番感じ取れるのはボーカルの若さでしょう。ここに「最近声変わりした形跡」があることに価値があると思うんですけど、この人たちの声はまさにそんな声です。ところで、ギターにクレジットされているデビッド・T・ワシントンってデビッド・T・ウォーカーじゃないのかな?ぽい音が随所で聴かれます。

山下達郎“SPACY” (1977)
今度はジャパニーズAORの至宝『SPACY』。歳上の友人の家で年末恒例のジャムセッションがあって。そこで見つけたら「持ってっていいよ」と軽く言われて腰が抜けそうになったという年の瀬の駆け込みエントリーです。
この時の達郎は24歳。声が若くて今よりもストレート。吉田美奈子の詩がイノセントで無垢な感じがするし、これも青春AORと言って良いのではないでしょうか?
ポンタさんのドラムがバーナード・パーディーみたいに「ダチーチー」してるし、そこに絡む細野さんのベースはチャック・レイニーのように黒くうねっています。奇しくも細野さんの50周年だった2019年の年の瀬のレココレは2号に渡って細野さん特集。『NO SMOKING』と『細野観光』を楽しんだぼくにとって、これは最高のプレゼントとなりました。

BEN SIDRAN“LIVE AT MONTREUX” (1978)
ベン・シドランには何枚かチャレンジしていて、惜しい感じで掠ってくるけどクリーンヒットしないもどかしをずっと持っていたアーティストです。思い切ってライブ盤を買ってみたらこれがスコーンとクリーンヒット。このトーキングスタイルのボーカルがライブのラフな緊張感に合っているんだと思います。でも。本当は言葉の意味がわかった方が数倍楽しめるアーティストなんでしょうねぇ〜(逆に白ける人もいます)。
ご機嫌なスティーブ・ジョーダンのドラムと、トニー・レヴィンのリズムセクションにブレッカー兄弟がホーンセクション。この時の映像が残っているので、「SONG FOR A SUCKER LIKE YOU」を貼っておきます。それにしもベン・シドランのヒップさって、本当にカッコいいですね。新しいのも含め追っていきたいアーティストです。
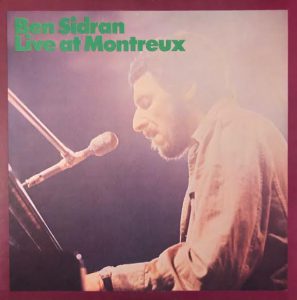
LINDA LEWIS“NOT A LITTLE GIRL ANYMORE” (1975)
リンダ・ルイスはムサレコの青木さんが『Lark』をかけて、そのコケティッシュなボーカルにやられ気になっていたアーティスト。アンテナを張り始めてぼくが初めて手にしたリンダのアルバムがこれです。UKソウルということなのか、ファンキーな臭さがあまりなく、グルーブでゴリゴリと押して来るというより作り込んで聴かせるタイプのポップな作りになっています。そう言った意味で音楽職人たちによって作られていたモータウンぽさを感じさせてくれる一枚です。
声は時にジャクソン5時代のマイケルを思い起こさせたり、マドンナのようでもありミニー・リパートンのようでもあるハイ・ボイス。このモジャモジャ頭の少年ぽさや少女っぽさと、タイトル曲の『NOT A LITTLE GIRL ANYMORE』で見せる大人っぽさのギャップがこの人の魅力なんだと思います。アップル・スタジオでフィル・マクドナルドによる録音がかなり生々しく、楽器のごとの分離が素晴らしくスタジオにいるようなレコードになっている点もポイント高いアルバムです。
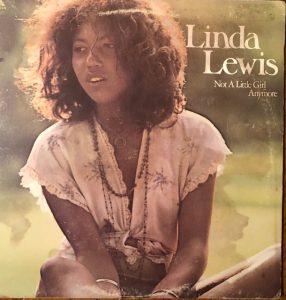
MINNIE RIPERTON“ADVENTURES IN PARADISE” (1975)
上記のリンダ・ルイスと同じ年にリリースされたミニー・リパートンのサードアルバム。こちらは、クルセイダーズからジョー・サンプルとラリー・カールトン、ドラムがジム・ゴードンなんですが、メッチャタイトで緻密で抑制の効いたドラミングにちょっとびっくりしました。その“緻密で抑制の効いた”というのがアルバム全体の印象で、隙間の多いアレンジの網の目を縫うようにミニーのボーカルが華麗に舞っている感じです。
そして、何と言ってもこのアルバムには「INSIDE MY LOVE」が収録されています。ミニーと言えば「LOVING YOU」がド定番ですが、ぼくの好みはこっちです。それにしてもジャケがいい!ライオンですよ!!オスですよ!!そしてアフロヘアーに生花のようにお花がいけてあります。これがチャーミング。特にインナースリーブのミニーが最高に可愛い!この4年後に31歳の若さで亡くなったことを考えると、このアルバムの記録媒体としての愛おしさを感じずにはいられません。

これが可愛いインナースリーブのミニー。

MARVIN GAYE“I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE” (1968)
ぼくがマービン・ゲイの『WHAT’S GOING ON』以前をアルバム聴きするようになったのは恥ずかしながら実は最近のことで、モータウンのベスト盤あたりに入っているマービンで満足していたんですよね。それでも、やはりムサレコでタミー・タレルとのデュエット盤なんかを聴かせもらって欲しくなったんですけど、なかなかないんですよね〜。
ぼくが見つけたこれは80年代のドイツのリイシュー盤なんですが、音がご機嫌にいい。特にベースがくっきりと輪郭を持って前に出てきている感じはベース好きのぼくとしては最高な一枚です。これはジェームス・ジェマーソンなんでしょうか?サム・クック的なスタイルから抜け出していく過程のマービンには、「I HEARD IT THROUGH THE GRAPEVINE」が必要だったんだと思いますが、その後の男女の関係でトラブル続きとなる人生を予見しているような歌ですね。ぼくのお気に入りは「CHAINED」です。
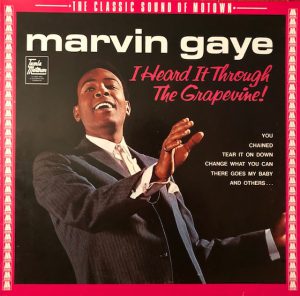
憂歌団“生聞59分‼︎” (1987)
これはCDでよく聴いていた一枚なんだけど、やっぱりアナログで欲しくて購入。正直に言ってCDの音を覚えていないくらい憂歌団から離れてしまっていて、違いを明言することができない。だけど、花岡さんのウッドベースがよく聴こえるような気がする。木村さんのライブはYoutubeでたまに観るんだけど、愛のこもった野次が本当に和気藹々としていいんですよね。あの感じが、この頃のライブですでにあって、愛すべきいじられキャラの木村さんを想像してニコニコしてよく聴きました。
今更ですが、内田勘太郎のよく歌うスライドギターが本当に素晴らしい。そして、バッキングに回った際の遊び心と冒険心に溢れるプレイが鉄壁の真逆を行っててミュージシャンシップを擽られます。そして何と言っても「ステイ・ウィズ・ユー・フォーエバー(君といつまでも)」での名カバーの名セリフ!日本にこういうバンドがいたことを誇りに思える一枚です。

JACO PASTORIUS“INVITAION” (1983)
これはハードオフで100円サルベージしたもの。CDでよく聴いていたジャコの日本でのライブを収めたもの。ジャケットの日本情緒のジャコの肖像画だけでも買う価値ある一枚。1曲目から飛ばしまくるこの日のジャコは本当に調子が良かったんでしょうね。会場に居た日本のファンの人たちが本当に羨ましい限りです。
このアルバムは2曲目の「AMERIKA」のベースソロから荘厳な次曲へのイントロの役割を果たす「SOUL INTRO」に続く「THE CHIKEN」が白眉で、こんなカッコいいビッグバンドは他にいないだろうし、これをベーシストであるジャコが作曲とアレンジをしているという点で驚愕します。そしてこのバンドの特異な点はスティールパン奏者がいることなんだけど、これが本当に気持ちがいい楽園感を醸し出しています。ウェザーリポートを脱退したジャコが本当にやりたかった音楽がここにあるっていう感じ。それにしても100円でここまで感動を味わえるなんて、ハードオフの巡回はやめられない。

JEAN JACQUES PERREY“MOOG INDIGO” (1970)
ぼくは今50歳(ムサレコ最年長)で、世代的にシンセサイザーにカルチャーショックを受けれた最後の世代なんじゃないかと思う。小学校高学年で聴いたYMOの「テクノポリス」のボコーダーによる「TOKYO」に度肝を抜かれた。あの時の衝撃が未だに残っており、ビンテージシンセの音、もっと言えばここで使われているモーグの音に弱いんです。そしてこのヘンテコ感とチープなオンボロ感。堪らないじゃないか!!
なんか意外なんだけど、このアルバムはMONOなんですよね。「PASSPORT TO THE FUTURE」なんて未来志向な曲を書いてて、MONO録音っていうのがなんとも解せない。パンニングで音をバンバン飛ばしたりしてスペーシーなサウンドを作るかと思いきや、音楽的センスは童謡的ですらある。この童謡的なるものが、「BAROQUE HOEDOWN」がディズニーランドのエレクトリカル・パレードに使われることになるんだろう。
21世紀の最初の10年が終わろうとしている時にレコードでこんなアルバムを聴きながら、家でMacBook Airで仕事をしている感じはとても不思議です。
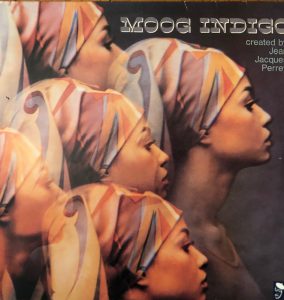
まあ、振り返って思うことは、ムサレコで他のメンバーからの刺激がなかったら一生聴いてなかっただろうなってアルバムがあるってことが喜びですね。耳は何歳になっても成長するんです。では、また。
